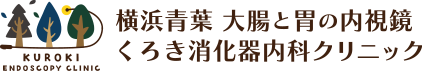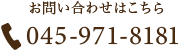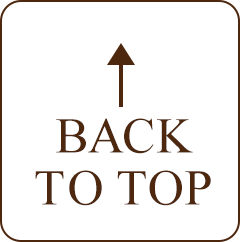健診で肝機能異常と言われた!原因・対処法は!?
肝機能異常 AST ALT 高い
|医師が解説する原因と生活習慣改善法
毎年の健康診断で「肝機能に異常がありますね」と言われて、びっくりした経験はありませんか?実は、健診を受けた方の約3人に1人が肝機能異常を指摘されています。「異常」という言葉を聞いて不安になるお気持ちはよく分かりますが、多くの場合は生活習慣を見直すことで改善できるものです。
消化器内科医としての長年診療に携わってきた経験から、健診の肝機能異常について分かりやすくお話しさせていただきます。
【健診の肝機能検査でチェックされる数値の意味と正常値】
まず、健康診断でチェックされる肝機能の数値について詳しく見ていきましょう。
- ■ AST(GOT)とALT(GPT):これらは肝細胞の中にある酵素(体の中で化学反応を助ける物質)です。肝細胞が壊れると血液中に漏れ出すため、この数値が高いということは肝臓にダメージがあることを示しています。正常値は一般的に30 IU/L以下とされています。
- ■ γ-GTP :これは胆汁(たんじゅう:肝臓で作られる消化液)に関係する酵素で、特にアルコールや薬によって上がりやすいものです。男性は50 IU/L以下、女性は30 IU/L以下が目安となっています。お酒をよく飲む方は気をつけたい数値ですね。
- ■ ALP: 正式名称はアルカリフォスファターゼといい、肝臓や骨、腸などにある酵素です。胆汁の流れが悪くなると高くなることが多いです。
- ■ ビリルビン :赤血球が古くなって壊れるときに作られる黄色い物質で、肝臓で処理されます。この値が高くなると、目や皮膚が黄色くなる黄疸(おうだん)という症状が現れます。
これらの数値が基準値を超えていても、軽度であれば慌てる必要はありません。大切なのは、なぜ異常になったのかを知り、適切に対処することです。
【肝機能異常の主な原因と症状を医師が解説】
肝機能異常の原因は実にさまざまですが、現代人に多いものから順にご説明していきます。
- ★ 脂肪肝(しぼうかん) 最も多い原因がこちらです。食べ過ぎや運動不足により、肝臓に脂肪がたまった状態を指します。フォアグラを想像していただけば分かりやすいでしょう。メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)と関係が深く、糖尿病や高血圧を合併することも多いです。
- ★ アルコール性肝障害 継続的な飲酒により肝臓が炎症を起こした状態です。「酒は百薬の長」という言葉もありますが、適量を超えると肝臓には大きな負担となります。毎日飲酒する習慣がある方は特に注意が必要です。
- ★ ウイルス性肝炎 B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスによる慢性的な炎症です。以前は治療が困難とされていましたが、現在は非常に効果的な治療薬が開発されています。
- ★ 薬剤性肝障害 薬やサプリメントが原因で起こる肝障害です。「天然だから安全」と思われがちなサプリメントでも、肝障害を起こすことがあります。
- ★ 自己免疫性肝疾患 自分の免疫システム(体を守る仕組み)が間違って肝臓を攻撃してしまう病気です。専門的な治療が必要となります。
症状について 肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期にはほとんど症状が現れません。しかし、以下のような症状がある場合は要注意です。
- ✔ だるさや疲れやすさが続く
- ✔ 食欲がない
- ✔ 右のお腹の上の方が重苦しい
- ✔ 目や皮膚が黄色くなる
- ✔ 尿の色が濃くなる
これらの症状がある場合は、早めに医療機関を受診されることをお勧めします。
【肝機能改善のための生活習慣と対処法】
肝機能異常を指摘されたとき、多くの方が「どうしたらよいのでしょう?」と困惑されます。ここでは具体的な改善方法をご紹介していきます。
食事の見直し まず重要なのが食生活の改善です。以下のポイントを意識してみてください。
- ◆ 腹八分目を心がける(食べ過ぎは肝臓に負担をかけます)
- ◆ 野菜を積極的に摂取する(1日350g以上が目標です)
- ◆ 魚や大豆製品などの良質なタンパク質を選ぶ
- ◆ 糖質や脂質の摂り過ぎに注意する
- ◆ 夜遅い時間の食事を避ける
運動習慣の確立 運動は脂肪肝の改善に特に効果的です。激しい運動は必要なく、以下のような有酸素運動を週3回、30分程度行うだけでも十分効果があります。
- ・ウォーキング
- ・ジョギング
- ・水泳
- ・サイクリング
筋力トレーニングも基礎代謝(何もしなくても消費されるエネルギー)を上げるため効果的です。
禁酒・節酒 アルコールが原因の場合、禁酒が最も効果的です。完全に止められない場合でも、最低週2日の休肝日を設けることが重要です。適量は日本酒1合、ビール中瓶1本程度とされています。
十分な睡眠とストレス管理 睡眠不足やストレスも肝機能に悪影響を与えます。7-8時間の質の良い睡眠を心がけ、趣味やリラクゼーションの時間を作ることも大切です。
定期的な検査 改善の効果を確認するため、3-6か月後に再検査を受けることをお勧めします。数値の変化を見ることで、生活習慣の改善効果を実感できるでしょう。
医療機関での精密検査 数値が高い場合や改善が見られない場合は、腹部超音波検査やCT、MRIなどでより詳しく肝臓の状態を調べる必要があります。ウイルス性肝炎の検査も重要です。
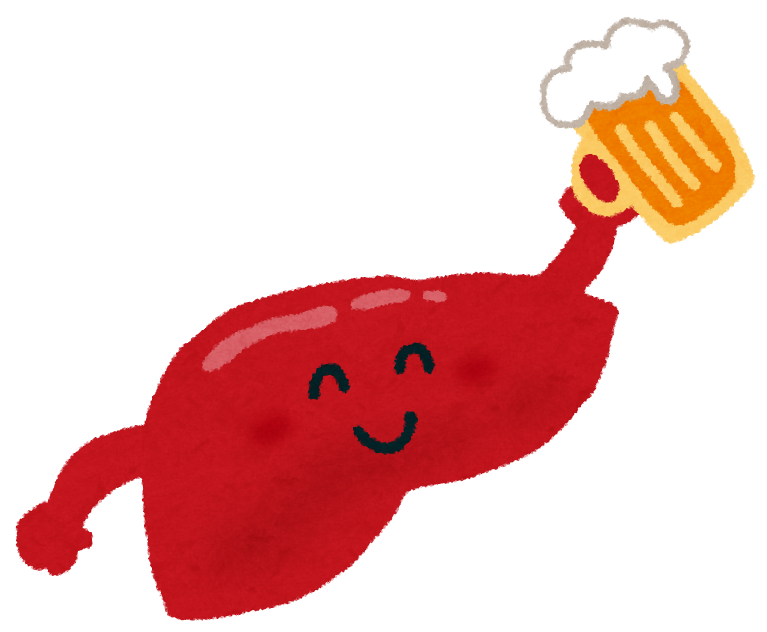
まとめ
健診で肝機能異常を指摘されても、多くの場合は生活習慣の改善で改善することができます。大切なのは結果を正しく理解し、適切な対応を取ることです。一人で悩まず、分からないことがあれば遠慮なく、当クリニックや最寄りの医療機関にご相談ください。